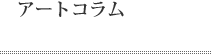2009年のアートコラム
現代日本画に見る桜の表現
2009.03.17
 現代日本画の桜表現は、巨木といわれる岐阜の淡墨桜、臥龍桜、山梨の神代桜、福島の滝桜などを中心に、生命感あふれる優美な捉え方に特徴があります。西行法師を敷衍した妖艶な桜、仏画や曼荼羅を思わせる桜、散り際の優美さなどもありますが、以前の淡白で比較的地味な山桜から、現代では花のウエーブが全山を覆うようなむんむんとした染井吉野の爛満桜へと進化を遂げ、千年桜を謳歌する天真爛漫さが際立ってきたようです。
現代日本画の桜表現は、巨木といわれる岐阜の淡墨桜、臥龍桜、山梨の神代桜、福島の滝桜などを中心に、生命感あふれる優美な捉え方に特徴があります。西行法師を敷衍した妖艶な桜、仏画や曼荼羅を思わせる桜、散り際の優美さなどもありますが、以前の淡白で比較的地味な山桜から、現代では花のウエーブが全山を覆うようなむんむんとした染井吉野の爛満桜へと進化を遂げ、千年桜を謳歌する天真爛漫さが際立ってきたようです。また、桜前線とともに春の風物詩となった満開の桜を堪能する展観は、日本の桜文化の厚みに思いを馳せる貴重な機会です。木葉之咲哉姫を祭神とする富士浅間神社は、桜と富士の相性の良さを伝えます。神話世界以来の精神文化を湛えた桜の日本画を、箱根富士の景観の中で見るのは特別な機会です。「星河流麗(久遠の桜)」の屏風他、圭吾桜(木村圭吾)を中心に、稗田一穂、近藤弘明、山本丘人、毛利武彦、平松礼二、岡信孝などの秀作を、春爛満の季節に全身で感じる一期一会の展観とは、美の結晶との出会い、小さな奇跡そのものでしょう。(学芸部)
城米彦造について
2009.06.30
〈僕が作った「詩」 僕自身で詩集にし、僕自身、賣ってゐるものです。よかったら買ってください。街頭詩人〉。そう書いたプラカードを胸に下げて、戦後の復興期に有楽町の街頭に立った男がいた。シルクハットを被った髭面の吟遊詩人画家は、あたかもチャップリンのごとき姿で、托鉢僧よろしくガード下に立ちつづけた。
武者小路実篤に心酔した「新しき村」の実践者・城米彦造は、サンドイッチマンのように自分自身の姿を世間にさらしながら、夢を追い続けた。家族とともに霞を食べて耐え、戦後の文化国家を支えつづけた民間の稀有な存在だった。
現代の円空や木喰のごとく、貧しくとも、清く、美しい瞳と心を持った筋金入りの一生であった。善意のみを信じた生涯だったといえよう。102歳の天寿を全うして、さる2006年に静かに息を引き取ったその平凡なる巨姿は、希代の赤裸々人生の一貫性という名の非凡なる生涯だったといっていい。
城米の淡彩スケッチは、いま振り返ると、同時代と鋭く対峙した記録である。そのスケッチの中には、時代が置き去りにしていった人間の匂いが満々とたたえられている。
近年、昭和30年代が見直されたが、それ以前からの戦後の庶民史が、城米の絵と詩には刻まれている。西岸良平の「三丁目の夕日」が映画化されたように、城米のノスタルジックな世界ももう一度かみしめたい。そこには戦後出立の頃の赤心の痕跡がある。(H・S)
中野嘉之の挑戦
2009.09.29
 京都出身でいま箱根にアトリエを構える画家が、中野嘉之です。これは考えてみると貴重な要素です。なぜなら東京と京都という二つの中心軸を持って誕生したのが近代日本画だからです。
京都出身でいま箱根にアトリエを構える画家が、中野嘉之です。これは考えてみると貴重な要素です。なぜなら東京と京都という二つの中心軸を持って誕生したのが近代日本画だからです。古くは明治時代から、京都から東京に出てきた川端玉章、岐阜生まれで京都の四条円山派を学んでから東上した川合玉堂、横浜生まれで神戸に育った東山魁夷などがいます。
竹内栖鳳は、横山大観と東西を分けた京都派の大御所でありながら、その晩年には伊豆の湯河原に住みました。逆に横山大観や速水御舟のように東京の画家でありながら、京都で青年時代のある時期、絵画研究をした画家もいます。
戦後の京都出身の画人に麻田鷹司がいます。中野嘉之の恩師である加山又造や森田曠平も京都出身ですが、東京で仕事をしました。
極論すると、狩野派の漢画的(そして洋風画的)な素養と、円山派の写生の素養の二つが近代日本画の基礎でした。
思うに、そうした先人たちの挑戦の上に立って、新たに展開する二十一世紀の日本画を創造する作業が、中野嘉之の使命の一つです。
今回の「京都季行」展は、先の「箱根十景」展とともに、中野嘉之にとって具体的なエリアを想定した貴重な試みです。
千二百年を超える京都の佇まいを描いた今回の連作は、画家にとって新境地となる重要な挑戦です。これまでどこにも見せたことのない京都人・中野嘉之の素顔がその表現の背後にはあります。(画像は中野嘉之「東山送り火」)